運送業の許可取得後から営業開始までの手続きについて解説
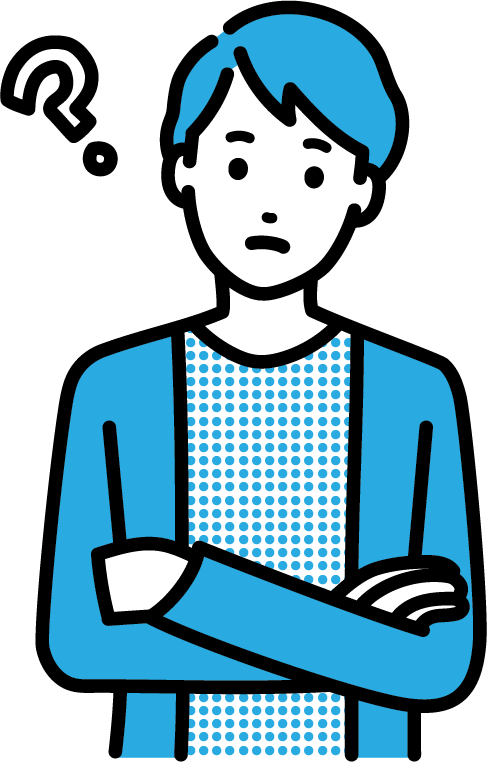
相談者様
運送業の許可を取得したらすぐに営業開始できますか?

行政書士
運送業は許可を取得してすぐに営業開始できるわけではなく、実際に営業を開始するまでに準備が必要となります。
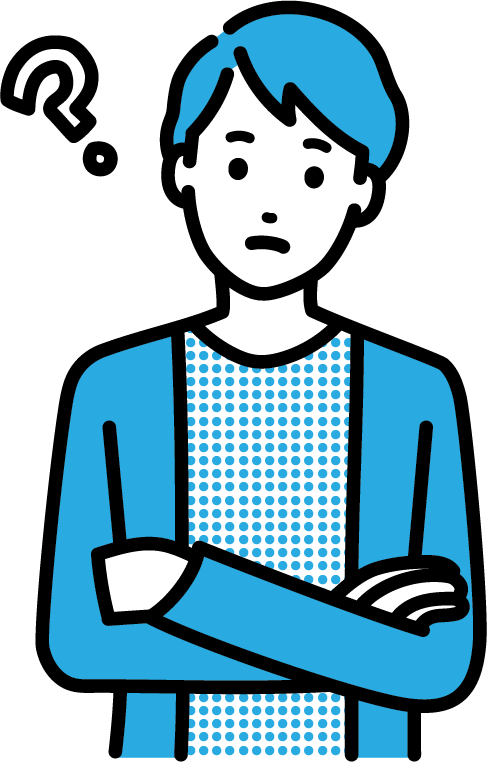
相談者様
どのような準備が必要ですか?

行政書士
運行管理者や整備管理者の選任、社会保険への加入手続きなど様々な手続きが必要です。この記事では、その手続きについて詳しく解説します。
許可証の交付
運輸局への許可申請後、法令試験に無事合格し、審査期間が過ぎると運輸局よりこのような連絡があります。

○○運輸さん、×月×日付けで許可になりました。
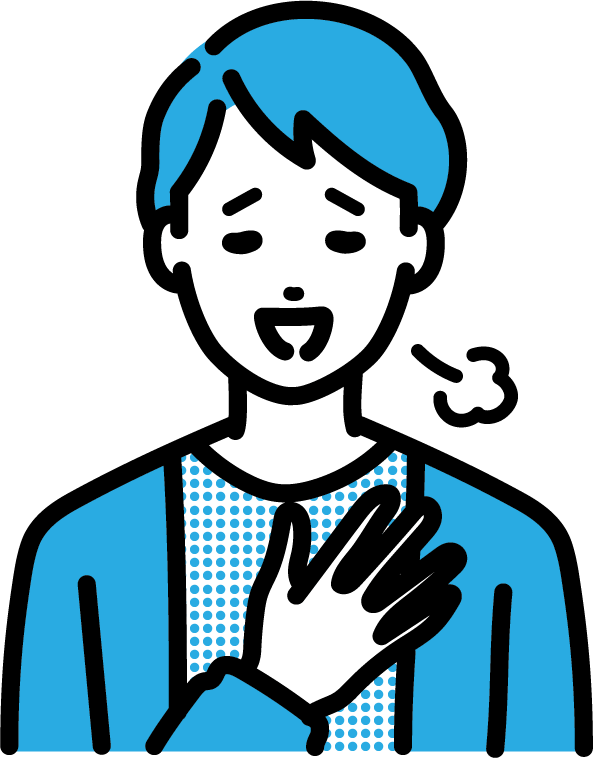
よかった、ありがとうございます。

△月△日に許可証の交付と今後の運営についての説明を行いますので、社長様か運行管理者様出席をお願いします。
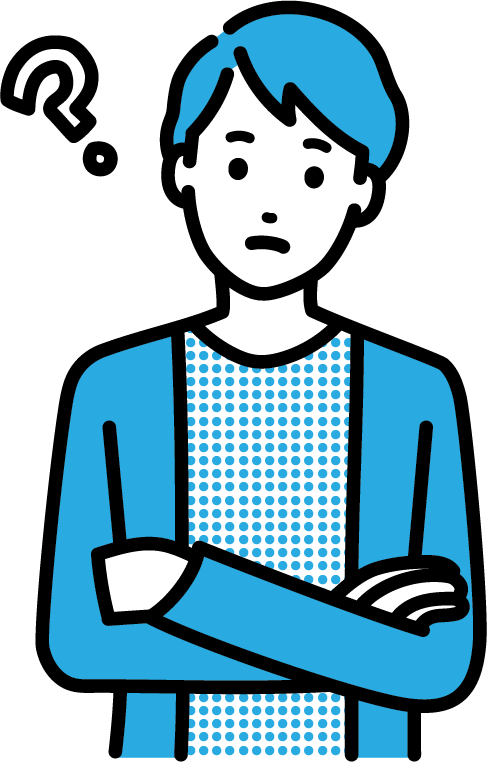
時間はどのくらいかかりますか?

約1時間程度です。筆記用具とメモ用紙等をお持ちのうえ、ご出席をお願いします。
会話にある通り、無事許可が下りると許可証の交付と今後の運営の説明が行われます。
愛知県の管轄である愛知運輸支局では、この許可証の交付と今後の説明のことを許可交付式と呼びますが、地域によって扱いは様々です。
また、一般貨物自動車運送業の許可を取得するには、登録免許税を納付する必要がありますが、このタイミングで納付書が渡される場合が多いです。
登録免許税の納付期限は1か月であるため、なるべく早めに郵便局や金融機関で納付を済ませましょう。
運行管理者・整備管理者の選任
許可が取得できると、運行管理者と整備管理者を正式に選任することができます。
もともと許可申請時に、両者の資格者証を添付しているかと思いますが、別の方を選任する事もできます。
運輸支局の窓口、もしくはホームページに載っている「運行管理者選任届」「整備管理者選任届」という書類に選任日や選任する方の情報を記載し、運輸支局の保安課等に提出します。
その際、運行管理者選任届には「運行管理者資格者証」を、整備管理者選任届には「整備士資格者証」もしくは「整備管理者選任前研修修了書」を添付します。
なお、この選任届は運輸局によって、許可が取得できれば許可交付式の前でも提出できる場合があるので、少しでも早く営業したい場合は運輸局に問い合わせてみても良いです。
社会保険への加入・36協定等の締結
運送業を開始するまでには、健康保険や雇用保険等の社会保険への加入を済ませておく必要があります。
加入や届け出が必要となる保険関係の手続きには下記の種類があります。
- 労働保険保険関係成立届の提出
- 雇用保険適用事業所設置届の提出
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届の提出
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の提出
- 36協定の提出
詳しくは、「運送業の営業開始するために必要な社会保険等について」にて解説しております。
なお、これらの手続きを許可申請中に済ませておくことで、許可取得から営業開始までの期間を短縮することができます。
運輸開始前確認
ここでは、「どの車両を事業用に登録するか」「運転手として誰を選任するか」を確定させ、申請書に記載します。
加えて選任する運転手の免許証コピーと、一つ前で解説した社会保険関係の書類の控えを申請書に添付します。
この申請書と添付する書類は「運輸開始前の確認について」といい、この書類が受理されるとナンバープレートを事業用に変更できる「事業用自動車等連絡書」が発行されます。
ナンバープレートの変更
「事業用自動車等連絡書」を取得出来たら、いよいよナンバープレートを事業用にします。
事業用ナンバーは、緑色であるため「緑ナンバー」とも呼ばれます。
新車で車両を用意する場合は、この連絡書をディーラーさんに渡せば事業用ナンバーで納車してもらえるはずです。
元々手元にある車両を事業用ナンバーにする場合は、管轄の陸運局に車両と連絡書を持ち込み、白ナンバーから緑ナンバーに変更します。
営業開始のための社内準備
ナンバーを事業用に変更出来たら、いよいよ営業開始に向けて社内準備を完了させます。
行うべき社内準備については、次のとおりです。
- 適性診断の受診
- 健康診断の受診
- 初任運転者研修の受講
- 運転記録証明書の取り寄せ
- 自動車任意保険の切り替え
- デジタコの導入
- 会社名等の車体表示
- ガソリンカード・ETCカードの準備
- 表札の記載
- 運賃料金表・運送約款の掲示
- 帳票類(運転者台帳、点呼記録簿、運転日報、日常点検表、運行管理規程、整備管理規程等)の準備
- アルコールチェッカーの準備
- 運行管理システムの配備
結構な量があるため、正直かなり大変かと思います。
しかし、この社内準備の中には、事業用ナンバーに変更する前であっても行う事が出来るものがほとんどです。
空いた時間を有効活用し、少しづつ準備を進めておくことで許可取得から営業開始までの日数を短縮しましょう。
運輸開始届・運賃料金設定届の提出
社内での準備が整ったらいよいよ営業開始です。
営業開始後は「運輸開始届」と「運賃料金設定届」を提出する必要があります。
運輸開始届には、事業用に変更した後の車両番号を記載し、車検証の写しと任意保険証券の写しを添付します。
運賃料金設定届には、営業開始日等を記載し、適用する運賃料金表を添付します。
これらの提出が終わり受理されれば、運送業の許可申請手続きについては、すべて終了になります。
ご相談はお気軽に
今回は、運送業の許可取得から営業開始までの手続きについて解説しました。
「運送業の許可は取得できたがその後の手続きが分からない」「運送業の許可取得手続きで疑問がある」という方はお気軽にお問い合わせください。
スマホの方は下記のメニューバーからお電話、メールいただけます。

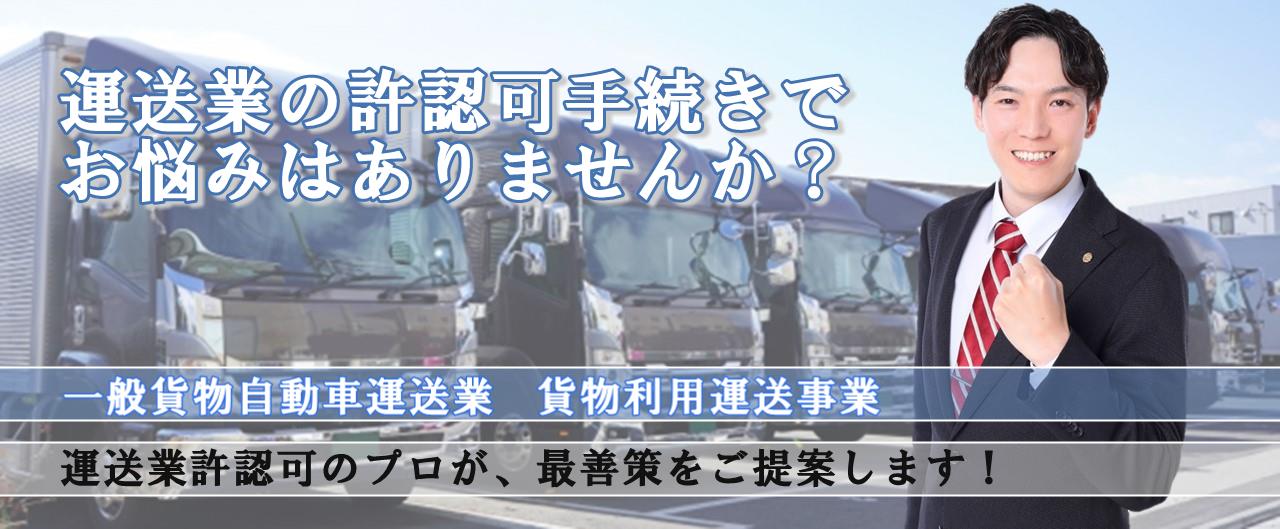
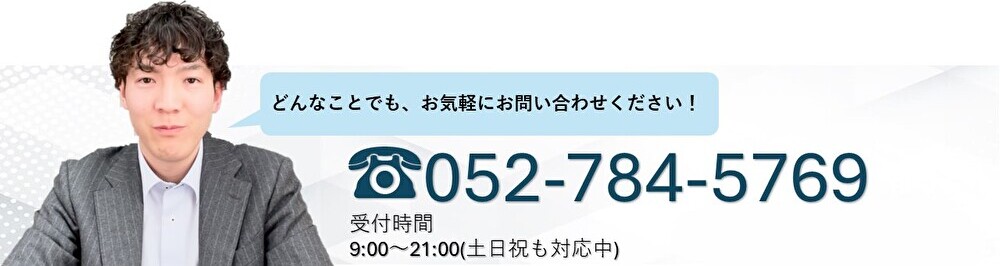

.jpg)






