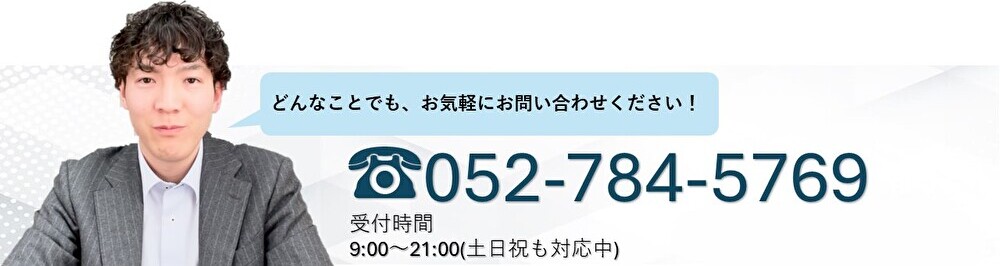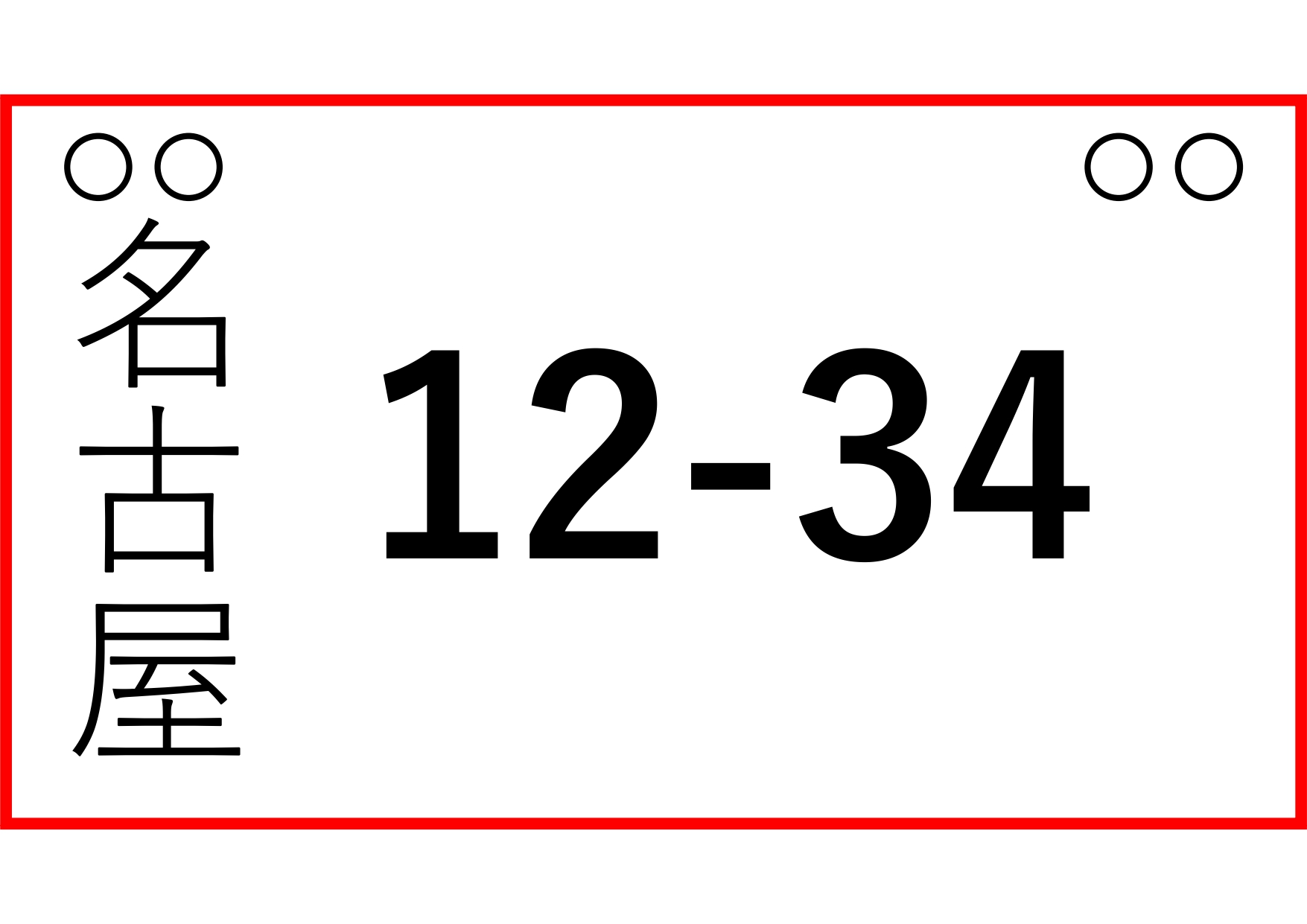貨物利用運送事業とは?登録申請の流れや許可の種類・要件を解説

貨物利用運送事業とは、自ら貨物の運搬する手段を持たず、運送の手配を行う事業を言います。
具体的には、荷物の運搬の依頼を受けたとき、荷主と運送の契約を結ぶのと同時に、運送会社とも契約を結びます。
そして、荷主から貰う運賃と運送会社に支払う運賃の差額を利益として、事業を運営していきます。
.jpg)
その昔、水を売る商人が、飛脚等への荷物の取り次ぎを行っていた事が由来で「水屋」と呼ばれることもあります。
また、利用運送会社が実際に運送を委託することや、委託先のトラック自体の事を「傭車」と呼ぶこともあります。
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業は行う事業内容によって、「第一種貨物利用運送」と「第二種貨物利用運送」に分かれます。
第一種貨物利用運送事業は、船舶・飛行機・列車・トラックのいずれか一つの輸送機関(一般的に「輸送モード」と言います。)使用し、輸送の手配を行います。
.jpg)
第二種貨物利用運送事業は、まずトラックでの荷物集荷、次に船舶・飛行機・列車いずれかのモードによる輸送、最後に輸送先である港・飛行場・仕向け駅から配達先へのトラック輸送を一貫して手配します。
.jpg)
このページでは、最もポピュラーな第一種貨物利用運送の自動車モードについての解説を行います。
貨物利用運送事業を行うには
貨物利用運送事業を行うためには、運輸局に申請し登録を得ることが必要です。
あくまで「登録」であるため、「許可」ではないですが、申請した結果登録とならない場合もあるので、実質「許可制」と同じ制度であると言えます。
未登録で営業した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が課せられます。
登録から事業開始までの流れ
登録の申請は次のような順番で進めます。
法人の設立
貨物利用運送事業の登録は法人でないと取得できないというわけではありませんが、始める方のほとんどが法人です。
具体的には、国土交通省が発表している中部エリアでの登録事業者は、直近年度(令和5年4月~令和6年3月)で法人が86社、個人が8名で、法人の割合が全体の約91%という事になります。
金融機関からの融資、節税対策や社会的信用の面から、法人で登録したほうが有利であることは間違いありません。
営業所の確保
後ほど、「貨物利用運送事業登録の要件」というタイトルで解説しますが、貨物利用運送事業の登録をするためにはクリアしなければならない条件(一般的に「要件」といいます。)があります。
その要件を満たすため、利用運送事業を営むための営業所を確保する必要があります。
これらの要件は登録の申請前に確保する必要があるため、この段階でどの物件を営業所にするか決めておきます。
利用運送契約を結ぶ
貨物利用運送事業の登録を受けるためには、あらかじめ荷物を運んでもらう運送会社と契約をしておく必要があります。
この契約のことを一般的に「利用運送契約」や「運送委託契約」と呼びます。
利用運送の登録前に、契約を結ぶのは違和感があるかもしれませんが、登録に必要であるため運送会社さんに話して契約を結んでもらうようにする必要があります。
また、この利用運送契約の締結は一つ上で解説した「営業所の確保」と同時並行で行います。
必要書類の収集
貨物利用運送事業の登録申請書には、記載する内容の証明のため多くの書類(一般的に「添付書類」といいます。)を用意する必要があります。
運送会社と結んだ「利用運送契約書のコピー」もその一部です。
その他にも会社の「履歴事項全部証明書」や「定款」、役員の「履歴書」などなど様々な添付書類を集める必要がります。
運輸局へ申請
登録のための要件を満たし、決められた添付書類を揃えることができたら、いよいよ申請書を作成し運輸局へ申請します。
申請から登録までの審査機関は、2ヶ月~3ヶ月と決められており短縮することはできません。
登録通知書の交付
審査期間が経過し、申請内容にも問題がない場合は、貨物利用運送事業の登録が完了します。
登録が完了すると「登録通知書」という許可証が交付され、同時に登録免許税という税金を納めるための納付書も一緒に渡されますので、金融機関で納付を済ませます。
利用運送の場合は、一般貨物自動車運送業の許可と異なり、登録が完了した時点で営業を開始することができます。
運賃料金設定届の提出
貨物利用運送の営業を開始したら、運賃として請求する料金の計算方法等を記載した運賃料金表を、運輸局に提出しなければなりません。
こちらも未提出の場合は、100万円以下の罰金があるので、必ず提出します。
こちらの書類を運輸局に提出して、一連の貨物利用運送事業の登録手続きが全て終了します。
貨物利用運送の登録要件
先程の「申請の流れ」でも少し解説しましたが、貨物利用運送の登録をするためには、一定の要件をクリアする必要があります。
要件は大きく分けると「ヒト」「モノ」「カネ」に分けることができます。
ではその要件を一つ一つ確認していきましょう。
「ヒト」に関する要件
申請する会社の役員が、ある一定の事項に該当する場合は、貨物利用運送事業の登録を受けることができなくなります。(欠格事由に該当すると言います。)
その該当してはいけない欠格事由は次の通りです。
1. 一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
3. 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
貨物利用運送事業法 第六条第一項より抜粋
万が一、役員がこれらの事項に該当している場合、その役員が退任しない限り登録を得ることができなくなるので、まず最初に確認しておきたい事項となります。
「モノ」に関する要件
モノ要件① 営業所
貨物利用運送事業の登録を得るには、事業を行う上で使用する「営業所」を用意する必要があります。
営業所については特に広さや設備に関しての決まりはなく、一般的な事務作業ができて休憩ができれば問題ありません。
自己所有でないといけないという縛りもなく、大家さんの承諾があれば賃貸でも大丈夫です。
ただ一つ注意すべきことは、営業所として使用できない場所が法律で決まっている(用途地域による制限といいます。)ため、物件を決めてしまう前に用途地域の調査が必要となります。
モノ要件② 保管施設
事業を行う上で、荷物を一時預かり保管するような場合は、保管施設を用意し登録する必要があります。
ただし、保管施設は営業所のように必ず確保しなければならないわけではなく、あくまで荷物を保管する場合のみ必要となる要件です。
保管施設も営業所と同じく用途地域による制限があるため、物件を決める前に用途地域の調査が必要となります。
「カネ」に関する要件
貨物利用運送事業の登録を受ける場合、直近年度の純資産額が300万円以上である必要があります。
純資産額は、会社の決算書の中の「貸借対照表」と呼ばれる書類に記載があります。
法人を設立したばかりで、まだ1期を迎えていない場合は、設立時の資本金が300万円以上であれば大丈夫です。
そのため、利用運送事業を行うために法人を立ち上げるた場合の資本金は、300万円以上にしておくことを強くお勧めします。
仮に純資産額が300万円未満の場合は、「増資」と呼ばれる手続きをすることにより、純資産額を増加させることができます。
増資とは、現金などの資産を会社に出資してもらうことで行う資金調達のことです。
当事務所で行うこと
当事務所では、まずはお客様の情報をヒアリングし、利用運送登録の申請が可能であるかを判断いたします。
現時点で許可の申請はできないと判断した場合、報酬をいただくことはありませんのでご安心ください。
すぐに申請可能、もしくはあと一歩で申請可能である場合には、今後行っていいただく事など適切なアドバイスを行い複雑な申請書作成や運輸局とのやり取りは、すべて当事務所にて行います。
また、既に利用運送登録をお持ちの方で、営業所や車庫等の変更手続きにつきましてももちろん当事務所にて承ることが可能です。
料金表
| 業務 | 料金(税込み) |
|---|---|
|
新規登録 |
110,000円 |
|
変更認可申請 |
55,000円~ |
|
変更届 |
22,000円~ |
|
実績報告書作成 |
11,000円 |
|
事業報告書作成 |
22,000円 |
※新規登録の場合、登録免許税として別途90,000円必要となります。