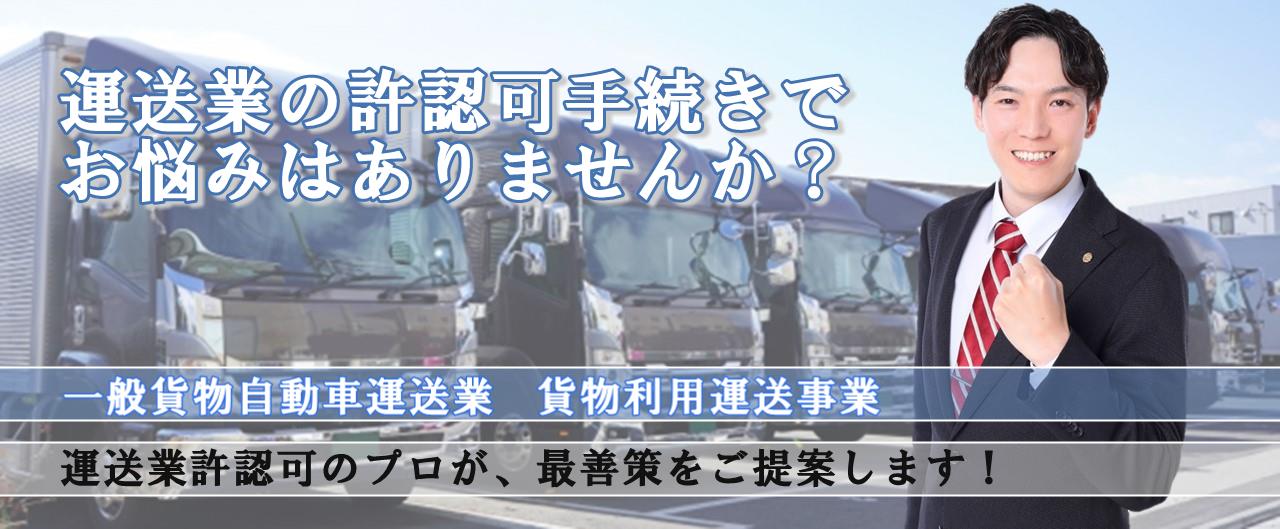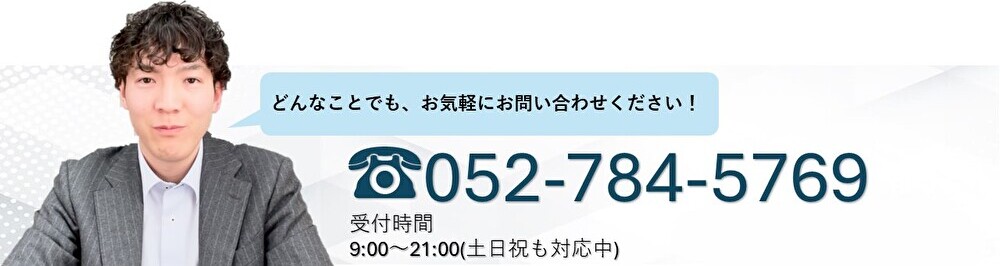運送業許可取得のために必要な資金条件について解説
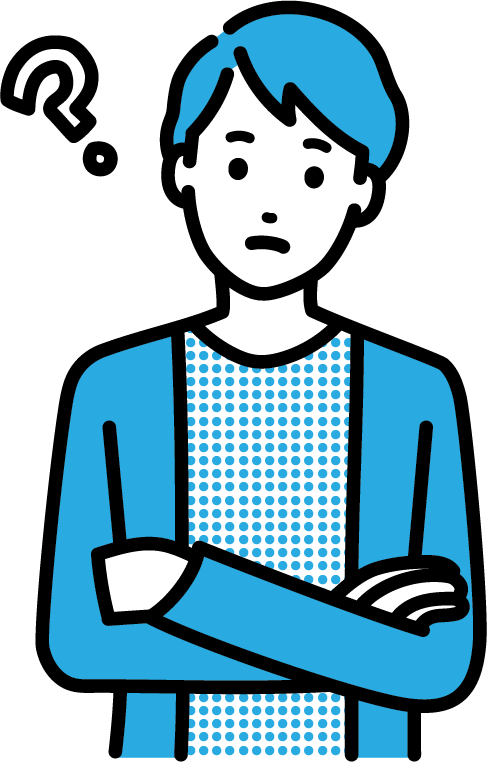
相談者様
運送業の許可は取得までどのくらい資金が必要なのでしょうか?

行政書士
約1500万円~2500万円必要といわれておりますが、事業者様によって大きく異なります。
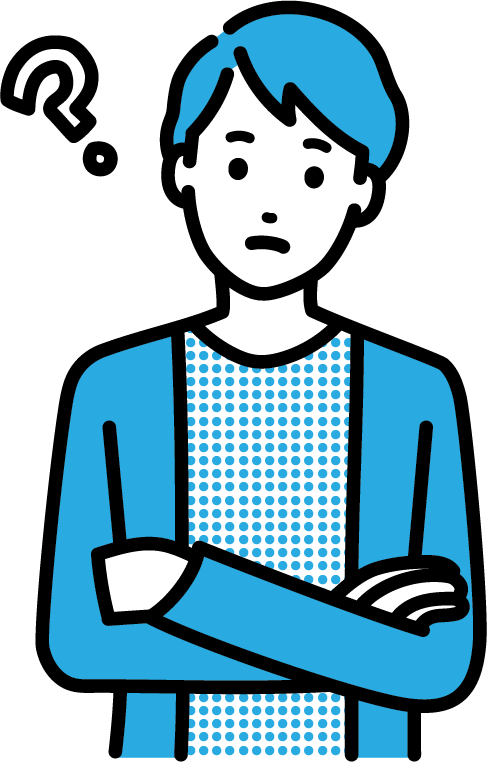
相談者様
結構かかるんですね、どうしてそんなに幅があるのですか?

行政書士
この金額は許可申請をする運送会社の、当面の運転資金を計算して算出されるからです。
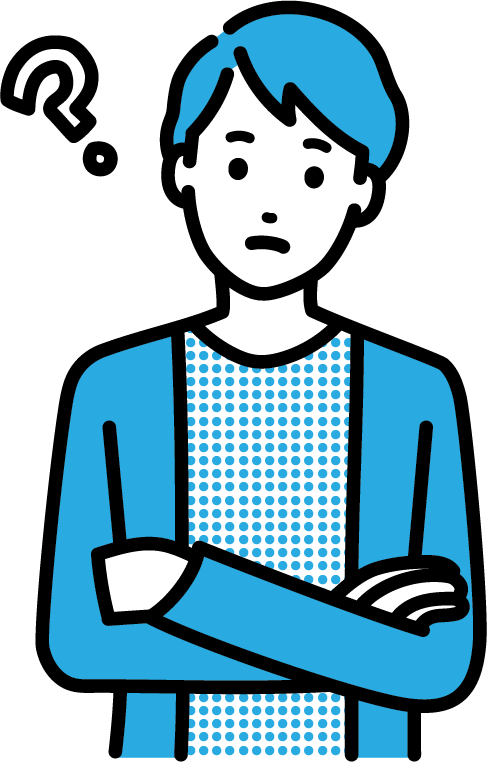
相談者様
何か算出の目安はないでしょうか?

行政書士
ざっくり言うと、1500万円+車両費が目安となりますが、正直状況をお伺いして計算してみないと正確な数字は分からないですね。
運送業の許可取得の要件
運送業の許可を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
この満たさなければならない条件を「要件」といい、大きく分けると「人員の要件」「設備の要件」「資金の要件」があります。
この記事では運送業許可取得のために必要な資金について、つまり「資金の要件」について具体的な内訳を交えて解説していきます。
なぜこれだけの資金が必要となるか?
なぜ許可を取るだけなのに、1500万円~2500万円という多額の資金が必要なのでしょうか?
運送会社というのは、我々の生活を支える物流インフラという公共性の高い側面を持っています。
このような「公共性のある事業が簡単に潰れては困る」と、許可を出す機関である国土交通省は考えているのです。
そのため、許可を出す場合は事業を継続することができるだけの潤沢な資金の確保を求めているわけです。
資金があることをどう証明するか?
運送業の許可を取るのに、多額の資金確保が条件になっていることは分かりました。
では、これほどの資金があるという事をどのように証明するのでしょうか?
実はこの証明は単純で、「会社の銀行口座にいくら入っているか」これだけです。
運送業許可の申請をする際に、分厚い申請書一式と一緒に残高証明書という書類も提出します。
残高証明書は、銀行の窓口に行って日付を指定すると発行してもらえて、その日の口座残高がいくらだったか記載されています。
その残高証明書の金額が1500万円~2500万円必要となる訳です。
さらに、その金額を申請から許可までの約4ヶ月間常に確保していなければならないという条件がついています。
申請から許可までの期間ということは、当然まだ運送業ができない状態です。
そんな中何千万という資金をプールしなければならないわけですから、なかなか難しい条件であることがお分かりいただけると思います。
必要となる資金の内訳
ここからは、その残高証明書の金額である、当面の運転資金の内訳を具体的に解説していきます。
一覧にすると次のような表になり、これらを全て合計すると平均して1500万円~2500万円になるという訳です。
| 費用の種類 | 期間 |
|---|---|
|
人件費 |
役員報酬を含む6ヶ月分 |
|
燃料費・油脂費及び修繕費 |
燃料油脂費及び修繕費のそれぞれ6ヶ月分 |
|
車両費 |
取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1年分のリース料 |
|
建物費 |
取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1年分の賃借料及び敷金等 |
|
土地費 |
取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1年分の賃借料 |
|
器具、工具什器、備品等 |
取得価格(割賦未払金を含む。) |
|
保険料 |
自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1年分 |
|
各種税 |
自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1年分、環境性能割及び登録免許税等 |
|
その他 |
道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分 |
人件費
役員報酬や運転手等の従業員の給料・賞与・手当を6ヶ月分を加えます。
さらに、法定福利費として従業員の健康保険料や雇用労災保険料を、福利厚生費として給与、手当、賞与の合計額の2%を見込んで計算します。
例として、役員が2人、運転手5人(整備管理者兼任)、運行管理者1人として考えると、人件費の項目だけで1100万円~1300万円程度になります。
燃料費・油脂費及び修繕費
燃料費としてトラック6ヶ月分のガソリン代を加えます。
5台スタートで、1日100km走るとすると、(100km×30日×6ヶ月)÷4.0km/ℓ×130円(軽油)=2,925,000円となります。
油脂費として、燃料費の2%を見込んで計上するので、2,925,000円×0.02=58,500円。
修繕費は6ヶ月分の修繕費やタイヤチューブ代を計上します。
特に計算式があるわけではないのですが、200万円前後を見ておく必要があります。
合計でおおよそ500万円前後見ておく必要があるという事ですね。
車両費
こちらはトラックの購入・リース費用です。
車両を新たに購入する場合は、その購入代金を加えます。
ただし一括購入で、申請する前に代金を全て払っている場合は、購入代金を加える必要はありません。
車両代を既に払っているのに、ここで費用に加えると二重で費用がかかる計算になってしまいますからね。
車両をリースやローンにする場合は、月々のリース代またはローン支払額を1年分加えます。
例として、5台すべてリースで月の支払いが80,000円とすると、80,000円×5台×12ヶ月=4,800,000円となります。
ただ極端な話、申請時点でトラックが全て自社所有であれば、こちらの車両費の項目は0円になるということです。
建物費・土地費
営業所として使用する建物と、車庫として使用する土地の購入費または賃料です。
考え方は車両費と同じで賃貸の場合は賃料1年分、物件を新たに購入または建築する場合は、その購入代金・建築費用を加えます。
これから購入・建築という場合は、当然ですが大幅に残高証明書の金額が上がります。
土地建物が自社所有、もしくは社長個人の所有物で無償で会社に貸し出すような場合は0円になります。
器具、工具什器、備品等
事務所の設備や備品などに必要な費用を加えます。
実務上数万円を計画に加えておけばよく、金額が少ないのであまり気にする必要はありません。
保険料
自賠責保険、自動車任意保険料の1年分を計上します。
任意保険の等級や補償内容によって金額が大きく異なりますが、100万円~200万円程度見ておく必要があります。
各種税
自動車税及び自動車重量税の1年分、環境性能割といった税金を計上する必要があります。
車両の規格にもよりますが、50万円~100万円程度見ておく必要があります。
その他
光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分とされていますが、実務上数万円を計画に加えておけばよく、金額が少ないのであまり気にする必要はありません。
おおよその目安
以上のような経費を合算して1500万円なり2000万円という数字が決まるので、当然その運送会社の荷物や車両の種類によって金額が変わります。
たとえば2tトラックで地場をメインとして仕事をする方と、大型トラックで長距離メインで仕事をする方では月々にかかる経費が全く違います。
ここまでの内訳をもとにおおよその目安を出すとすると次のようになります。
車両リース代なしで事務所車庫が自社所有であれば、1500万円~2000万円前後
車両のリースの残債があり、事務所車庫賃貸の場合で、2000万円~2500万円前後
さらに車両が大型車でかつ、新車リースの場合は3000万円以上
しかし、この金額もあくまで感覚であり、正確に計算してみないことにはわからないということはご了承ください。
売掛金がある場合は資金を抑えることが出来る
ここで裏ワザとまでは言いませんが、あまり知られていない残高証明書の金額を抑えるテクニックをお伝えします。
実は既に事業を行っていて、常に月々の売掛金が発生している場合は、その売掛金を資金として組み込むことが出来る場合があります。
たとえば建設会社さんが運送業許可を取得するような場合で、月々の売掛金が平均して500万円あるとします。
今回必要な資金が1500万円であった場合、売掛金500万円を差し引いて、法人の銀行口座に準備しておくお金は1000万円で済むという事です。
このように売掛金が常にある場合は、(売掛金の金額)+(法人の口座残高)=許可取得に必要な資金として考えることができるわけです。