Gマーク申請の必要書類を解説(輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施編)
こちらの記事は、「Gマーク申請の必要書類を解説(運転者等の指導・教育編)」の続きとなります。
Gマークの申請は、下記の4項目に関する書類を用意し、トラック協会に提出する必要があります。
- 運転者等の指導・教育
- 輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施
- 法定基準を上回る対策の実施
- その他
前回の記事では、①の「運転者等の指導・教育」に関する必要書類を解説しました。
なので今回の記事では、②の「輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施」に関する必要書類を解説します。
「輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施」と聞くと難しく聞こえますが、「うちの会社は安全のための会議を実施しました」ということがトラック協会に伝わればいいわけです。
こちらの項目もさらに次の3つの小項目に分かれ、それぞれ用意する書類が微妙に異なります。
- 事業所内での安全対策会議の定期的な実施[優先度:A]
- 事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施[優先度:B]
- 荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施[優先度:B]
前回の記事と同様、筆者の独断で優先度をつけています。
こちらは一つの項目をクリアすることで、2点獲得することができます。
なお、3つの項目すべて実施する必要はなく、最低1項目、最大2項目選択して実施することができます。
つまり、1項目実施なら2点、2項目実施すれば満点の4点獲得することができます。
運転者等の指導・教育は下記の4項目に分かれ、最低1項目、最大3項目クリアする必要があり、1項目の配点は3点でした。
- 自社内独自の運転者研修等の実施[優先度:A]
- 外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣[優先度:A]
- 定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施[優先度:B]
- 安全運につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施[優先度:C]
それでは、これから3つの小項目について必要書類を踏まえて解説します。
事業所内での安全対策会議の定期的な実施[優先度:A]
この項目は、自社で輸送の安全に関する会議を実施することで2点得点されます。
3つある項目の中で一番取組み易いので、優先度はAとしています。
というよりも、この項目は確実に点をとらなければなりません。
実施期間については、 過去1年間での実績を評価するパターンと、過去3年間での実績を評価するパターンの2つがあり、どちらを選択しても良いです。
ちなみに過去1年間というのは、その年のGマーク申請時である7月1日から過去1年間(つまり昨年7月2日~今年7月1日までの1年間)ということで、過去3年間であっても考え方は同じです。
過去1年分のパターンについては、その1年間において、会議を2 回以上実施すれば加点。
過去3年間のパターンについては、その3年間において、会議を毎年1 回以上(つまり3年間で最低3回)実施すれば加点です。
おすすめは、過去1年間のパターンでの申請です。
- あくまで安全に関する会議の実施が必要なので、従業員に対する指導や実習などは加点対象とならない
- 構内作業や積荷、荷卸作業などの交通事故防止に直接関わりのない会議は加点の対象とならない
- 月例の車両に係る交通事故防止会議
- 交通事故防止等輸送の安全確保に関するミーティング
- 会議の議事録コピー
- 会議に使用した資料コピー
①議事録と記載していますが、書類の名前は何でもよく、おこなった会議の内容が分かればいいとされています。
ただし、議事録からは実施日、実施場所、会議への参加者、会議の内容は最低限読み取れることが必要です。
②の資料としては、会議で使用した書籍やスライドを印刷した書面が一般的でしょう。
実施したことのアピールとして、会議風景を写した写真などを添付しても良いかと思います。
資料については、これを添付すれば間違いないというような明確な規定はありませんので、Gマーク認定の審査をする側の方の立場に立って、取組みの事実をなるべくわかりやすく伝えられる資料を付けることが大切です。
事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施[優先度:B]
個人的に、Gマーク申請の取組史上、最も何をすればよいのかわからない項目だと思っています。
この項目は、自社で安全に関するQC活動もしくは、小グループによる安全活動を実施することで2点得点されます。
ですが、QC活動や安全活動など抽象的過ぎてどのような取組みをすればよいのか困るところです。
優先度はCにしたいですが、最後の項目もそこそこキツイのでBとしています。
実施期間については、Gマーク申請時である7月1日から過去3年間ということで、期間については易しめに設定されています。
回数の規定もないので、1回以上実施が確認できれば良いとされているようです。
- 他社が実施する活動への参加や、申請する営業所以外が主催する活動は加点されず、あくまで自社のGマークを申請する営業所が主催する活動でなければならない
- 構内作業や積荷、荷卸作業などの交通事故防止に直接関わりのない活動は加点の対象とならない
不明
- QC活動の内容が分かる議事録コピー
- 小グループでの安全活動の取り組みが分かる資料のコピー
もしくは
具体的な取組み内容は不明ですが、QC活動の方はおそらく何か「現状課題を抱えたテーマ」を決め、改善に向けて活動をおこなうという事でしょう。
たとえば、現状見通しが悪く事故が多発するヤードの出入口があり、その事故の防止策を営業所で話し合った結果、カーブミラーの設置と近くの学校の登下校時間の交通誘導を行うのがいいのではないかという結論が出たとします。
その結論をもとにそれらの改善策を自社で実施し、その結果事故が減少しました。といったレポートを作成するイメージでしょうか。
一応Gマークの案内に、提出する議事録に載せる内容として、「テーマの策定」、「現状の把握」、「改善方法」、「改善に向けた目標の設定」、「活動計画策定」、「活動の実施報告」、「活動の効果」、「問題点・課題」、「まとめ」、「グループのメンバー」等を記載するとあります。
聞くところによると、「輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施」の中でも、この項目を選択する会社は少ないという事なので、取組みの事実をなるべくわかりやすく伝えられる資料を付けることが大切です。
荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施[優先度:B]
この項目は分かりやすいです。
一番最初に解説した、「事業所内での安全対策会議の定期的な実施」の複数企業バージョンです。
自社に加えて、最低もう一社他の会社と合同で輸送の安全に関する会議を行います。
会社は、荷主、下請会社、親会社、子会社、その他関連会社等どのような会社でもいいようです。
自社だけで完結することが出来ない部分がネックなので、優先度はBとしていますが、先程のQC活動の項目をパスするのであれば加点しておきたい項目です。
実施期間と会議の回数についても「事業所内での安全対策会議の定期的な実施」と全く一緒で、 過去1年間での実績を評価するパターンと、過去3年間での実績を評価するパターンの2つがあり、どちらを選択しても良いです。
過去1年分のパターンは1年間に2 回以上、過去3年間のパターンは、3年間で毎年1 回以上です。
こちらもおすすめは、過去1年間のパターンでの申請です。
- 貨物軽自動車運送事業者や配達業務を委託する個人との共同は加点の対象とならない
- 共同して会議を行う企業は、毎回同じ企業でなければならない
- 月例の車両に係る交通事故防止会議
- 交通事故防止等輸送の安全確保に関するミーティング
- 会議の議事録コピー
- 会議に使用した資料コピー
注意点としては、共同で会議を行う企業は毎回バラバラではダメという事です。
必要書類については、自社での安全会議と一緒で①議事録と記載していますが、書類の名前は何でもよく、おこなった会議の内容が分かればいいとされています。
ただし、議事録からは実施日、実施場所、会議への参加者、会議の内容は最低限読み取れることが必要です。
会議への参加者には、もちろん自社の従業員だけではなく、相手の会社の従業員も記載しなければならないものだと思われます。
②の資料としては、会議で使用した書籍やスライドを印刷した書面が一般的でしょう。
実施したことのアピールとして、会議風景を写した写真などを添付しても良いかと思います。
まとめ
今回は「運転者等の指導・教育編」ということで、解説をしてみました。
これから次の項目である「法定基準を上回る対策の実施」へと続きますので、Gマーク申請を考えている事業者様は是非チェックしてみてください。

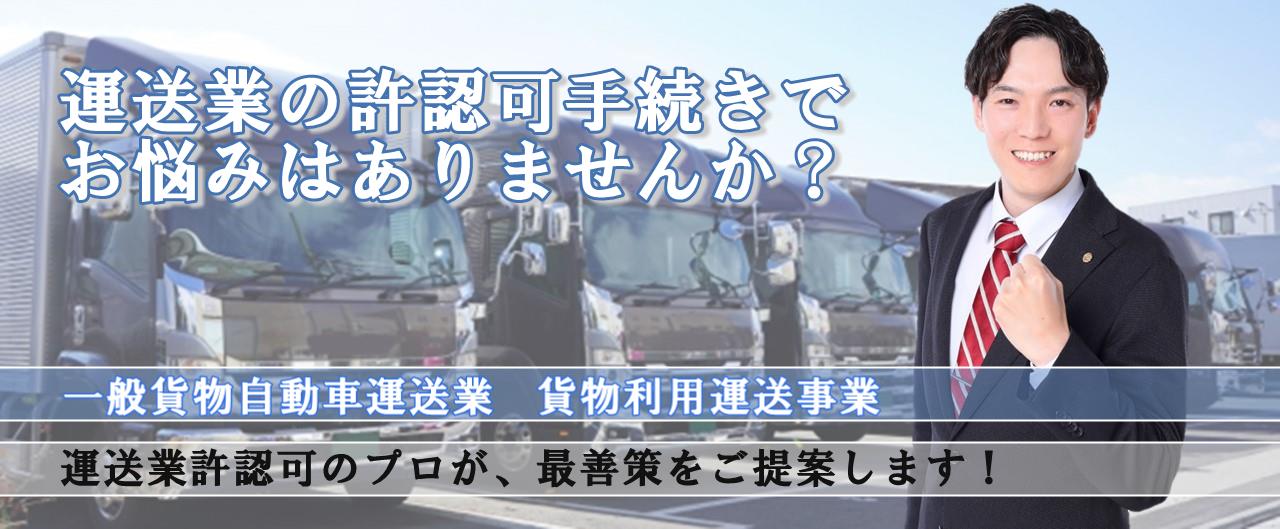

.jpg)






