Gマーク申請の必要書類を解説(法定基準を上回る対策の実施編)
こちらの記事は、「Gマーク申請の必要書類を解説輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施」の続きとなります。
おさらいですが、Gマークの申請は、下記の4項目に関する書類を用意し、トラック協会に提出する必要があります。
- 運転者等の指導・教育
- 輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施
- 法定基準を上回る対策の実施
- その他
前回と前々回の記事では、①の「運転者等の指導・教育」、②の「輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施」のに関する必要書類を解説しました。
なので今回の記事では、③の「定基準を上回る対策の実施」に関する必要書類を解説します。
こちらの項目もさらに次の4つの小項目に分かれ、それぞれ用意する書類が微妙に異なります。
- 特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている[優先度:A]
- 効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施[優先度:B]
- 車両の安全性を向上させる装置の装着[優先度:A]
- ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況[優先度:B]
前回の記事と同様、筆者の独断で優先度をつけています。
こちらは一つの項目をクリアすることで、2点獲得することができます。
なお、4つの項目すべて実施する必要はなく、最低1項目、最大2項目選択して実施することができます。
つまり、1項目実施なら2点、2項目実施すれば満点の4点獲得することができます。
輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施は下記の3項目に分かれ、最低1項目、最大2項目クリアする必要があり、1項目の配点は2点でした。
- 事業所内での安全対策会議の定期的な実施[優先度:A]
- 事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施[優先度:B]
- 荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施[優先度:B]
それでは、これから4つの小項目について必要書類を踏まえて解説します。
特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている[優先度:A]
この項目は、自社の運転手に対して適性診断を受講してもらうことで2点得点されます。
受講するだけで得点になり、4つある項目の中で一番取組み易いので、優先度はAとしています。
受診すべき期間については、 過去1年間での受診パターンと、過去3年間での受診パターンの2つがあり、どちらを選択しても良いです。
ちなみに過去1年間というのは、その年のGマーク申請時である7月1日から過去1年間(つまり昨年7月2日~今年7月1日までの1年間)ということで、過去3年間であっても考え方は同じです。
過去1年分のパターンについては、その1年間において、「適性診断(一般診断)」の受診者数が、全ての運転者数の 3 割以上であれば加点。
過去3年間のパターンについては、その3年間において、「適性診断(一般診断又は特定の運転者に対する診断)」を運転者全員が受診していれば加点です。
- 過去1年間分のパターンの場合は、特定の運転者に対する診断は加点の対象にならない
- 損害保険会社等の行う自己診断や自己チェックのみで診断結果が出ていないものは、加点の対象とならない
ここでいう「特定の運転者に対する診断」とは、次の表にある特定診断、初任診断、適齢診断を指します。
| 特定の運転者 | 適性診断の種類 |
|---|---|
| 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者(事故惹起運転者) | 特定診断Ⅰ、Ⅱ |
| 運転者として新たに雇い入れた者(初任運転者) | 初任診断 |
| 高齢者(65 歳以上の者をいう。)(高齢運転者) | 適齢診断 |
つまり、過去1年間で申請するパターンにおいて、最近雇い入れた運転手などの特定の運転者がいる場合、初任診断に加えて、一般診断も受講しないと加点の対象にならないという事です。
- 自社の運転手3割もしくは全員が適性診断を受診する
- 受診結果(運転者個人の受診結果又は受診結果一覧表)のコピー
効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施[優先度:B]
健康起因による事故防止に効果があるとされる、脳検査やSAS(睡眠時無呼吸症候群)の検査を行う事で、加点の対象となります。
実施の期間は、その年のGマーク申請時である7月1日から過去1年間(つまり昨年7月2日~今年7月1日までの1年間)でです。
必要となる人数については、下記の表のとおり取組み内容によって異なります。
| 取り組み内容 |
実施が必要な |
|---|---|
| 健康診断結果のフォローアップ | 規定なし |
| 脳検査(脳ドック、脳 MRI 健診、脳 CT スキャン)の受診 |
1 割以上かつ |
| 携帯型⼼電計の活⽤ | 2 割以上 |
| SAS(CAPA等の機器レンタル、終夜睡眠ポリグラフ検査を含む)検査 | 2 割以上 |
健康診断結果のフォローアップとは、健康診断で再検査の対象となった者に受診を促す等、健康診断結果を活用した健康起因事故防止対策を行っていることを指すようです。
またSAS検査については、既に SAS の治療中である運転者がいる場合、その運転者が治療を受けていることを証明する書類の提出をすることで加点の対象になります。
健康診断結果のフォローアップ、脳検査、心電計、SASのうちいずれかの実施
- 健康診断結果のフォローアップをしていることがわかる資料(健康診断結果のフォローアップの場合)
- 検査結果通知書および領収書等のコピー(脳検査受診の場合)
- 直近の機器管理によるドライバーの測定状況がわかる資料および機器の写真(携帯型心電計の場合)
- 検査結果通知書および領収書等のコピーなど(SAS 検査の場合)
車両の安全性を向上させる装置の装着[優先度:A]
自社の事業用トラックに、事故を予防するための装置(車線感知装置や先行ライトなど)を導入することで加点となる項目です。
最低1台の導入でよく、そもそも既に導入しているというパターンも多いため優先度はAです。
装置の導入日については、特に規定はなくGマーク申請時である7月1日時点で、1台以上導入が完了していれば加点です。
- 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)
- 車間距離制御装置+車線維持支援制御装置
- ドライバー異常時対応システム
- 先進ライト
- 側方衝突警報装置
- アルコールインターロック
- 事故自動通報システム
- ドライブレコーダー(1点)
- バックアイカメラ(1点)
次のような装置を自社の事業用トラックに導入する
※装置の種類はGマーク申請年度によって多少変更あり
- 機器のカタログコピー
- 機器の設置状況が確認できる写真
- 機器を設置した⾞両のナンバーの分かる写真
- 機器を設置した⾞両の⾞検証
導入すべき機器については、その年の補助金対象機器と連動するため、Gマークの申請年度によって多少異なります。
「機器の設置状況が確認できる写真」は、⾞内に設置してある機器本体及び付属装置(カメラやセンサーなど)を撮影します。
機器によっては写真に写すことができない事もあるため、その場合は「搭載証明書」や「購入時の領収書のコピー」などで代用します。
「機器設置⾞両のナンバーの分かる写真」は、⾞両の正⾯から車体とナンバープレートが写真に収まるように撮影します。
- Gマーク申請年度によって、加点対象となる機器が異なる可能性がある
- 「ドライブレコーダー」または「後方視野確認支援装置(バックアイカメラ)」のみの導入は点数が2点から1点に下がる
- 複数台に導入されていたとしても、車両台数に応じて点数が加算される訳ではない
ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況[優先度:B]
36 協定届において、ドライバーの時間外労働時間の上限である 960 時間を下回る届出が確認できれば加点とします。
運送業においては、残業や休日出勤などのいわゆる時間外労働が発生する場合がほとんどであると考えられます。
そのためほとんどの運送会社にて、「時間外労働及び休日労働に関する協定書」であるいわゆる「36(サブロク)協定」を届け出ていると思います。
現在の法律では、36協定書を届け出ていたとしても、ドライバーの時間外労働の上限は年間960時間までです。
なので通常は上限の960時間にて届け出ていると思うのですが、この項目では960時間を下回る届出がされていれば加点です。
長くなりましたが、要は「うちの会社は上限ギリギリの残業をさせるつもりはなく、余裕を持った労働環境を整えていますよ」ということがトラック協会に伝わればいいのです。
極端な事をいえば、その年度の36協定にて、時間外労働時間を959 時間にて届出をすれば加点という事です。
36協定については、自社にて作成している場合もあれば、社会保険労務士さんに作成してもらっている場合も多いと思いますので、36協定の作成者と相談して時間外労働時間を定めるのが良いでしょう。
時間外労働時間の上限規制 である960 時間を下回る36協定書を労働基準監督署に提出する
36協定書コピー
- 36協定書の業務の種類欄に自動車運転者として記載されている必要がある
- 労働基準監督署の受付印が押印されており、Gマーク申請時点において36協定書の有効期限が切れていないことが条件
まとめ
今回は「運転者等の指導・教育編」ということで、解説をしてみました。
これから次の項目である「その他」へと続きますので、Gマーク申請を考えている事業者様は是非チェックしてみてください。

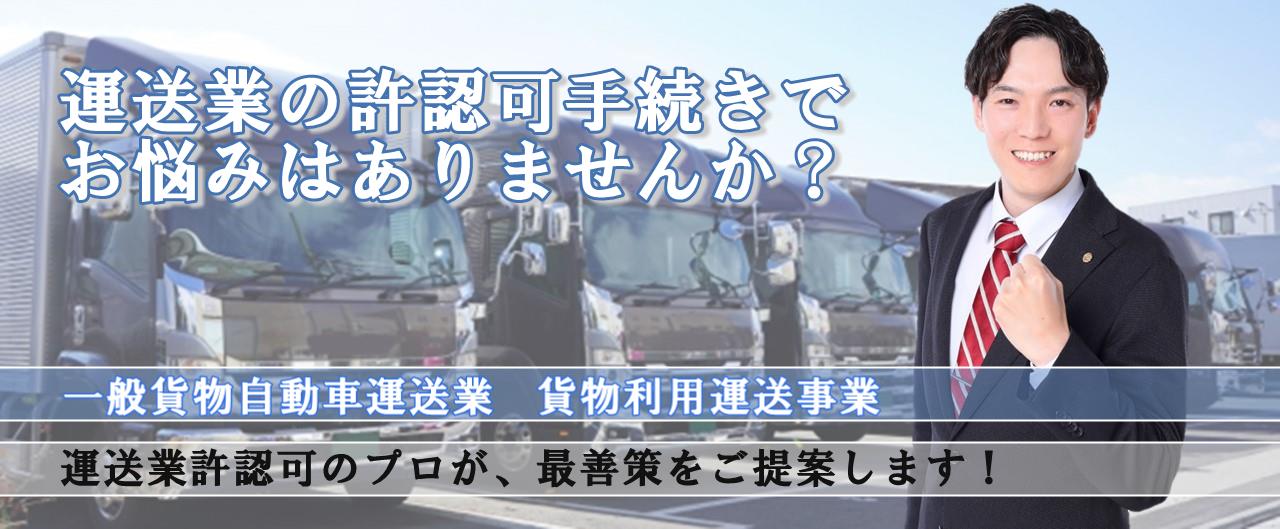

.jpg)






