Gマーク申請の必要書類を解説(その他編)
こちらの記事は、「Gマーク申請の必要書類を解説(法定基準を上回る対策の実施編)」の続きとなります。
おさらいですが、Gマークの申請は、下記の4項目に関する書類を用意し、トラック協会に提出する必要があります。
- 運転者等の指導・教育
- 輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施
- 法定基準を上回る対策の実施
- その他
前回までの3つの記事で、④その他以外に関する必要書類を解説しましたので、今回は最後のその他項目について必要書類を解説します。
その他項目はさらに次の6つの小項目に分かれ、それぞれ用意する書類が異なります。
- 健康起因事故防止に向けた取組[優先度:A]
- 輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得[優先度:C]
- 国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審[優先度:C]
- 過去3年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績[優先度:C]
- リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入[優先度:B]
- 自社内独自の無事故運転者表彰制度または省エネ運転認定制度の活用[優先度:C]
前回の記事と同様、筆者の独断で優先度をつけています。
その他項目は、他の項目に比べて配点が低いため、そのそもの優先度が低めです。
こちらは一つの項目をクリアすることで、1点獲得することができます。
なお、6つの項目すべて実施する必要はなく、最低1項目、最大3項目選択して実施することができます。
法定基準を上回る対策の実施は下記の4項目に分かれ、最低1項目、最大2項目クリアする必要があり、1項目の配点は2点でした。
- 特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている[優先度:A]
- 効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施[優先度:B]
- 車両の安全性を向上させる装置の装着[優先度:A]
- ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況[優先度:B]
それでは、これから6つの小項目について必要書類を踏まえて解説します。
健康起因事故防止に向けた取組[優先度:A]
健康起因による、事故防止に効果があるとされる取組みを自社で行う事で加点の対象となります。
実はほぼ同じような項目が別グループにありました。
それが前回解説した「法定基準を上回る対策の実施」の2番目に紹介した「効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施」です。
こちらの項目は、脳検査やSAS検査を病院等で実施することで加点となりました。
今回は、これら脳検査やSAS検査以外で、何か健康起因による事故を防止するような取組みを行えば加点となります。
実施の期間は、その年のGマーク申請時である7月1日から過去1年間(つまり昨年7月2日~今年7月1日までの1年間)です。
- 点呼時にドライバーの血圧及び体温を計測して管理している
- 社内報などにに定期的に食事や健康に関する記事を載せている
- 会社にトレーニングルームを設けている
- 福利厚生としてスポーツジムと契約している
- 会社として健康経営優良法人の認定を取得している など
主に次のような健康維持のための取り組み
- 体温・血圧管理表コピー
- 健康に関する記事が載っている社内報などのコピー
- 会社にあるトレーニングルームの写真
- 会社とスポーツジムとの契約書コピー
- 健康経営優良法人認定書コピー
なお、これらの取組はあくまでひとつの例であるため、従業員のために会社として健康維持に関する取組みをおこなっていれば、それを証明する書類を提出することで加点の対象となるはずです。
- 資料から継続的な取り組みであることが判別できなければ加点対象とならない
- 定期健康診断の受診など法令で義務づけられている取り組みは加点の対象とならない
継続的または定期的な取組みである必要があるので、たとえば提出書類として「1ヶ月分の管理表しかない」や「スポーツジムとの契約が期間限定である」というような場合は、加点の対象とならないと思われます。
輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得[優先度:C]
自社で行った安全や環境への功績について、外部の機関から何らかの認定がされていれば加点の対象となります。
- グリーン経営認証
- エコステージ認証
- エコアクション 21 認証
- ISO9000 シリーズ(品質マネジメントシステム)
- ISO14000 シリーズ(環境マネジメントシステム)
- ISO39000 シリーズ(道路交通安全マネジメントシステム)
主に次のような認定を取得している
このようにかなり具体的に、加点の対象が決められています。
ですが、貨物輸送を対象とする安全や環境に関する認証であれば、これら以外にも加点の対象となるはずです。
優先度はCで、何か認定があれば良し、特になければ別の項目を狙っていいと思います。
認定証または登録証のコピー
国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審[優先度:C]
国が認定する機関により、運輸安全マネジメント評価が実施されていれば加点になります。
運輸安全マネジメントとは、簡単に言うと会社のトップが輸送安全の向上のための取組みを主導し、会社全体に安全意識の浸透を図り、計画的に会社全体の安全性の向上を図るための仕組みです。
これらの仕組みである運輸安全マネジメントを、国が認定する機関に調査してもらい、評価を受けることができます。
評価実施の期間は、その年のGマーク申請時である7月1日から過去2年間(つまり一昨年7月2日~今年7月1日までの2年間)です。
- 独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)
- MS & AD インターリスク総研 株式会社
- SOMPO リスクマネジメント 株式会社
- 東京海上ディーアール 株式会社
- 一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)
- 一般社団法人 日本海事検定協会(NKKK)
主に次のような機関に運輸安全マネジメント評価を実施してもらう
(令和 6 年 4 月現在)
一般的には、これらの調査機関に運輸安全マネジメント評価の申し込み、手数料を払って書面による調査や会社への訪問による調査・評価をしてもらうことになります。
運輸マネジメント評価報告書のコピー
評価報告書のうち、「Ref. No.」「評価日」「事業者名称」「署名:評価チームリーダー」の内容が確認できるページのコピーを提出する必要があるようです。
過去3年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績[優先度:C]
自社の輸送の安全や交通安全等の取り組みに対して、外部の機関から表彰されていれば加点の対象となります。
二つ前に解説した「輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得」に似ています。
表彰された時期は、その年のGマーク申請時である7月1日から過去3年間である必要があります。
- 国土交通省、地方運輸局、運輸支局等
- 警察庁、都道府県警察本部、警察署等
- トラック協会本部・支部
- 陸上労働災害防止協会(陸災防)
- トラック交通共済協同組合 など
主に次のような機関から表彰をされている
表彰状のコピーまたは表彰状・表彰盾を写した写真
- Gマークを申請する営業所に対する表彰でないと加点の対象とならない
表彰状に会社の名称しか記載されていない場合は、トラック協会に提出する前に、営業所の名前を付記する必要があります。
リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入[優先度:B]
自社でGPS機能を活用した運行管理システムを活用していれば加点の対象となります。
よくあるのが、営業所のパソコンで自社トラックの位置がアプリの地図上に表示されるシステムです。
既にこのようなシステムを導入されている会社様は、是非この項目は加点いただきたいです。
GPS と連動した運行管理を行うシステムの導入・活用
- 機器類のカタログコピー
- 機器の設置状況が確認できる写真
- 機器を設置した⾞両のナンバーの分かる写真
- 機器を設置した⾞両の⾞検証
- システムを利用して車両の運行管理を行っていることがわかるパソコンの画面の写真
「機器の設置状況が確認できる写真」は、⾞内に設置してある機器本体を撮影します。
「機器設置⾞両のナンバーの分かる写真」は、⾞両の正⾯から車体とナンバープレートが写真に収まるように撮影します。
最後のパソコン画面の写真には、日付と導入している車両のナンバーが写っていることが必要です。
自社内独自の無事故運転者表彰制度または省エネ運転認定制度の活用[優先度:C]
自社にて、ドライバーに対する事故防止や省エネ運転に関する表彰制度を策定している場合は加点の対象となります。
具体的に言うと、「1年間無事故無違反だった運転手に対し、年度末に表彰および金一封を授与する」という規定を設けている場合などが該当するでしょう。
無事故や省エネ運転に関する表彰又は認定制度を導入し、実際に実施している
- 制度要綱や認定要領、手当の支給制度などの具体的な取組内容を記載した書類
- 表彰状のコピーまたは表彰盾などの写真
- 手当を支給した事が分かる明細書など(表彰だけでなく手当を支給している場合)
表彰や手当の支給等について、未だ実績がない場合は、要綱、要領等に実績がないことを書き添える必要があります。

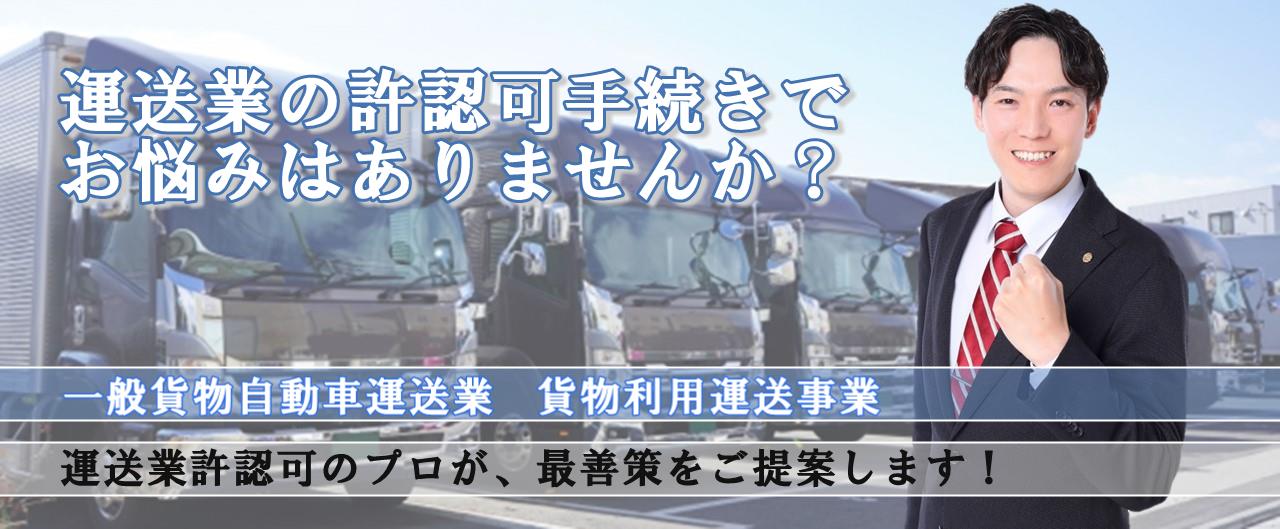

.jpg)






