事業用自動車等連絡書の書き方や必要書類を解説!
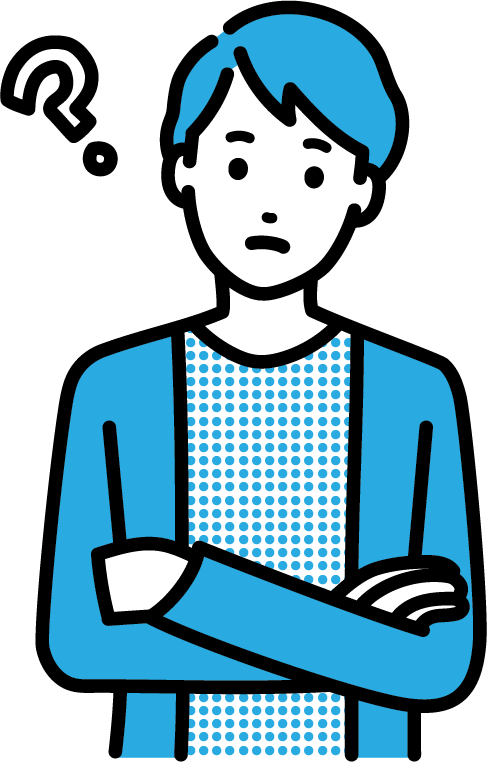
相談者様
事業用自動車等連絡書とは何ですか?

行政書士
その名の通り、事業用の自動車(緑ナンバートラックやバス・タクシーなど)の車検証やナンバーを変更する時に必ず必要となる書類です。
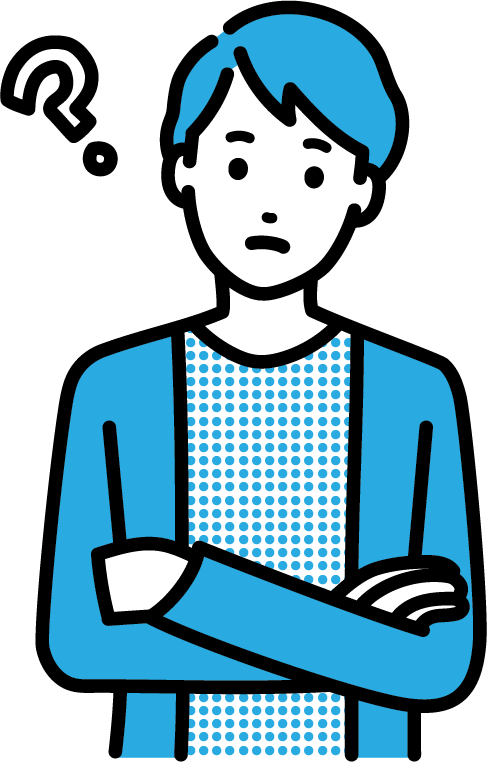
相談者様
なるほど、その事業用自動車等連絡書はどうやって入手するのですか?

行政書士
基本的に管轄の運輸支局に申請することで取得することができます。
今回の記事では、事業用自動車等連絡書について徹底解説します。
なお、名前が長いのでここからは単に「連絡書」とさせていただきます。
事業用自動車等連絡書とは
さて初めにもう一度連絡書について、どのような役割の書類なのか解説します。
まず連絡書は、事業用自動車に関する手続きでしか登場しません。
ここでいう事業用自動車とは、緑色のナンバープレートがついているトラック・バス・タクシー・ハイヤー・霊柩車・バイク、あと黒色のナンバープレートが付いている軽自動車です。
連絡書はこれらの車両の手続き以外では登場しませんし、逆にこれらの車両の車検証変更手続きには必ず必要となります。
たとえば、下記のような手続きには必ず連絡書が必要となります。
- トラックを自家用(白)ナンバーから事業用(緑)ナンバーにする、または事業用ナンバーから自家用ナンバーに戻す
- バイクを自家用ナンバーから事業用ナンバーにする、または事業用ナンバーから自家用ナンバーに戻す
- 軽自動車を自家用(黄)ナンバーから事業用(黒)ナンバーにする、または事業用ナンバーから自家用ナンバーに戻す
- 事業用ナンバーのバスの所有者または使用者を変更する
- 事業用ナンバータクシーを名古屋ナンバーから尾張小牧ナンバーにする
- 事業用ナンバー霊柩車の使用の本拠の位置を変更する
挙げればキリがないので上記の手続きはほんの一例ですが、とにかく連絡書は事業用ナンバー車両の変更手続きには毎回登場します。
事業用自動車等連絡書の取得方法
さて、連絡書が事業用自動車の変更手続きに欠かすことができない書類だということはご理解いただけたかと思います。
では肝心の事業用連絡書の取得方法ですが、管轄の運輸支局という役所で手続きをすることで発行することができます。
なお管轄の考え方ですが、事業用自動車は車検証に記載されている「使用の本拠の位置」を基準に決まります。
例えば事業用ナンバーのトラックを自家用ナンバーにしたい場合は、現在の車検証に記載されている「使用の本拠の位置」になっている都道府県の運輸支局で手続きを行います。
運輸支局は基本的に各都道府県に1つあるので「使用の本拠の位置」が愛知県名古屋市・・・なら「愛知運輸支局」、北海道札幌市・・・なら「北海道運輸支局」という具合になります。
ただ、ここで気を付けたいのが自家用ナンバーから事業用ナンバーにする場合です。
この場合は、変更後の車検証に記載される「使用の本拠の位置」が基準となります。
現在の自家用ナンバーに記載されている「使用の本拠の位置」が基準ではないので注意しましょう。
事業用自動車等連絡書を取得するための必要書類
次に事業用自動車等連絡書を取得するための必要書類を解説します。
なお、事業用自動車等連絡書はトラックやバス・タクシーなど様々な種類の車両に使用されるうえ、変更の内容も名義変更やナンバーの種類変更など多岐にわたります。
そのため、どの種類の車両にどのような変更をするのかによってかなり必要書類が異なります。
それぞれ分けて解説をします。
ナンバーを自家用からから事業用にする
白ナンバーから緑ナンバー(軽の場合は黄から黒)にする手続きで、おそらく一番需要の多い手続きではないでしょうか?
初めて事業用にする
これから運送事業を始めようとする方が該当します。
始めて車両を事業用にする時は、それぞれの事業を始めるための許可を取得する必要がありますので、下記の必要書類を管轄の運輸支局に提出する必要があります。
| 車両の種類 | 必要書類 | 連絡書発行までの期間 |
|---|---|---|
|
トラック |
一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書 | 3~5ヶ月 |
| 貸切バス | 一般貸切旅客自動車運送事業の経営許可申請書 | 4ヶ月 |
|
タクシー |
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)経営許可申請書 | 3ヶ月 |
|
軽自動車 |
貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 即日 |
既に事業用自動車があり増車する
すでに許可を取得している事業者様については、下記のような事業の車両台数に関する変更届(一般的に「増減車届」といいます。)を提出することによって、基本的に提出したその日に連絡書を取得することができます。
| 車両の種類 | 必要書類 | 連絡書発行までの期間 |
|---|---|---|
|
トラック |
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書(増車・減車) | 即日 |
| 貸切バス | 一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更届 | 即日 |
|
タクシー |
一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出書 | 即日 |
|
軽自動車 |
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 | 即日 |
なお増減車届を提出するにあたって、注意しなければならない点が1点ありまして、それが車庫の収容能力です。
収容能力というのは、その車庫の大きさに対して何台分の事業用自動車が収まるかという事です。
この収容率が90%以上の場合、つまり既に車庫に車両が多数停まっていて、これ以上収容するのは難しそうだという場合は、認可申請となり連絡書発行まで数ヶ月かかる場合があります。
ナンバーを事業用からから自家用にする
緑ナンバーから白ナンバー(軽の場合は黒から黄)にする手続きです。
こちらも、廃業によって自家用に戻す場合と、特定の車両だけ自家用に戻す場合で手続きが異なります。
事業を廃業する
今まで営業してきた運送事業の廃止に伴って、トラックやバスについていた事業用ナンバーを自家用ナンバーに戻すパターンがこちらに該当します。
許可申請と違い、廃止に関する手続きは原則即日受理され、その日のうちに自家用ナンバーに戻すための連絡書が発行されます。
| 車両の種類 | 必要書類 | 連絡書発行までの期間 |
|---|---|---|
|
トラック |
事業廃止届出書 | 即日 |
| 貸切バス | 同上 | 即日 |
|
タクシー |
同上 | 即日 |
|
軽自動車 |
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 | 即日 |
なお、一時的に事業を休止する「休止届」という手続きも存在します。
この休止届を提出した際も、自家用ナンバーに戻すための連絡書が発行され、再び事業用に戻す際には、再開届(または再開計画申請書)を提出し事業用に戻すための連絡書を発行してもらいます。
特定の車両だけ減車する
事業は継続し、ある特定の車両だけ自家用に戻す場合が該当します。
この場合は、先ほど解説した増車する場合と同様に「増減車届」を提出することにより、自家用ナンバーに戻すための連絡書が即日発行されます。
運送会社Aから運送会社Bへ、事業用のまま車両を移動させる場合は、運送会社Aで減車届、運送会社Bで増車届を提出します。
そうすると、A社名義の減車連絡書、B社名義の増車連絡書が発行されるので、その2枚を登録窓口に提出することによってA社-B社間の車両の移動ができます。
車検証の使用者の氏名または名称・住所を変更する
事業用自動車の名義が変わる場合も連絡書が必要となります。
名義や住所が変わる場合、大きく分けて次の2パターンがあります。
合併・分割・相続により名義が変更となる
会社の合併や、事業主の相続により車両の名義が変更となる場合が該当します。
| 車両の種類 | 必要書類 | 連絡書発行までの期間 |
|---|---|---|
|
トラック |
相続による継続認可申請書 |
1~3ヶ月 |
| 貸切バス | 同上 | 3~4ヶ月 |
|
タクシー |
同上 | 2~3ヶ月 |
|
軽自動車 |
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 | 即日 |
会社の組織再編や、個人事業主の相続などによって事業用自動車の名義に変更が生じる場合は、管轄の運輸支局に認可申請をし、認可にならないと連絡書は発行されません。
上記以外の理由で名義または住所が変更となる
単に会社名を変えることとなった場合や、会社の本店所在地を移転した場合がこちらに該当します。
| 車両の種類 | 必要書類 | 連絡書発行までの期間 |
|---|---|---|
|
トラック |
住所・名称・役員変更届出書 | 即日 |
| 貸切バス | 同上 | 即日 |
|
タクシー |
同上 | 即日 |
|
軽自動車 |
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 | 即日 |
こちらは合併や相続と違い、変更届を管轄の運輸支局に提出し受理されれば、変更にかかる連絡書が発行されます。
ナンバーの管轄が変わった(使用の本拠の位置変更)
たとえば事業用自動車が名古屋ナンバーから尾張小牧ナンバーに変更になった場合などが該当します。
また、ナンバーの管轄に変更がなくても、使用の本拠の位置を変更する場合も連絡書が必要となります。
| 車両の種類 | 必要書類 | 連絡書発行までの期間 |
|---|---|---|
|
トラック |
事業計画変更認可申請書 | 1~3ヶ月 |
| 貸切バス | 同上 | 4ヶ月 |
|
タクシー |
同上 | 2ヶ月 |
|
軽自動車 |
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 | 即日 |
事業用自動車では、「使用の本拠の位置の変更=営業所の位置の変更」となります。
ということで、車検証上の使用の本拠の位置を変更したい場合は、管轄の運輸支局に運送業の営業所変更の申請をし、認可を取得する必要があります。
こちらが認可となると、その営業所に所属する車両に関する「使用の本拠の位置を変更するための連絡書」が発行されます。
事業用自動車等連絡書の書き方
最後に連絡書の記載方法を紹介します。
ですが、中部運輸局管轄の運輸支局の多くは、連絡書は自分で記載しなくても窓口側で作成してもらえます。
_page-0001 (1).jpg)
- 事業等の種別:一般貨物であれば「一般」、貸切バスであれば「貸切」という具体に該当する業種に〇をつけます
- 使用者の名称:現在の使用者名義を車検証通りに記載します。ただし、名義を変更するための連絡書の場合は変更後の名義を記載します
- 使用者の住所:現在の使用者住所を車検証通りに記載します。ただし、住所を変えるための連絡書の場合は変更後の住所を記載します
- 所属営業所名:事業用自動車が所属する運送業の営業所名を記載します
- 使用の本拠の位置:④の営業所の所在地を記載します
- 自動車登録番号等:車検証を見ながら車両の情報を記載します
- 事案発生理由:連絡書を発行する理由に○をつけます

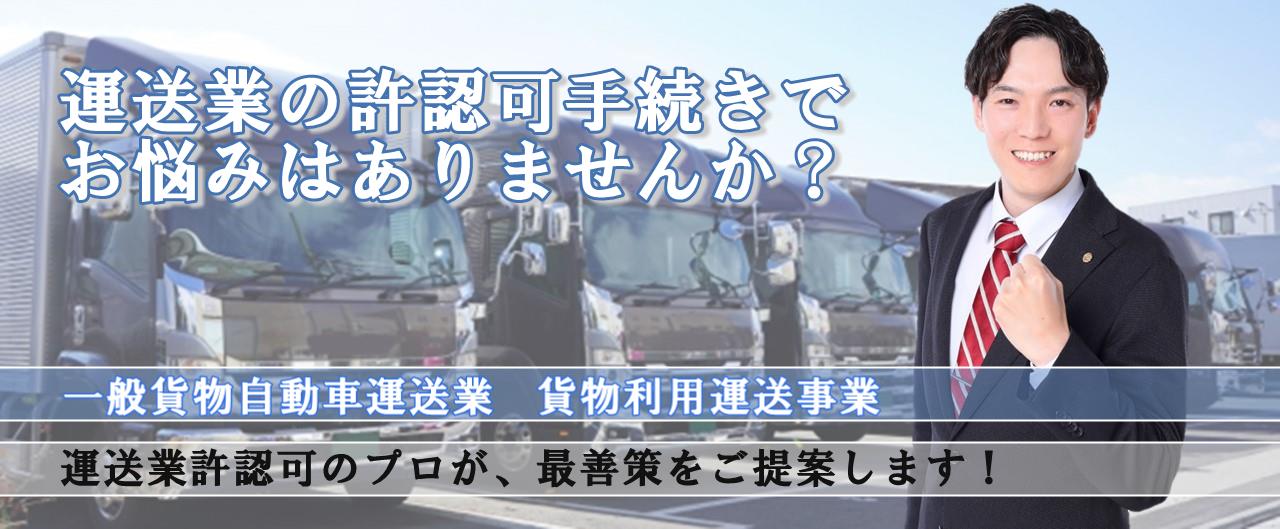
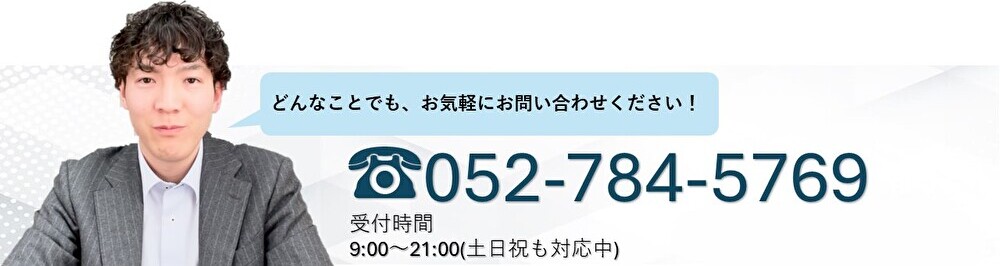

.jpg)






