関東地方(埼玉・神奈川・東京・千葉)でのディーラーナンバー取得条件を解説!
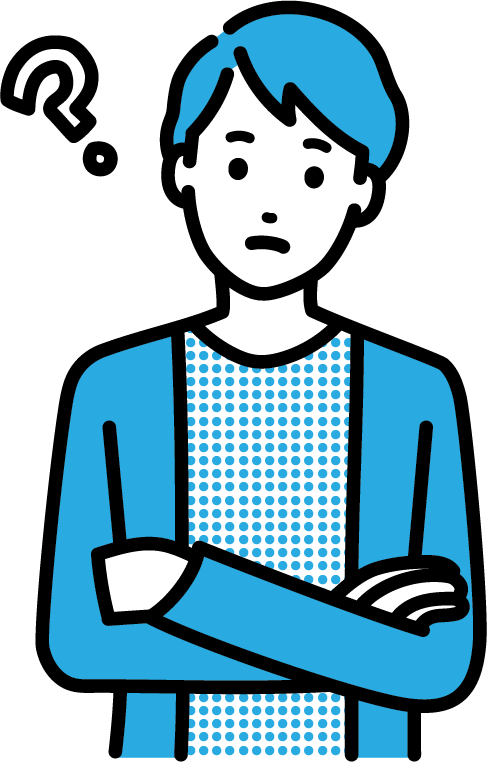
相談者様
ディーラーナンバーの取得条件を教えてください。

行政書士
ディーラーナンバーは地域によって取得条件が異なります。ナンバーを使用するための自事務所はどちらの都道府県にありますか?
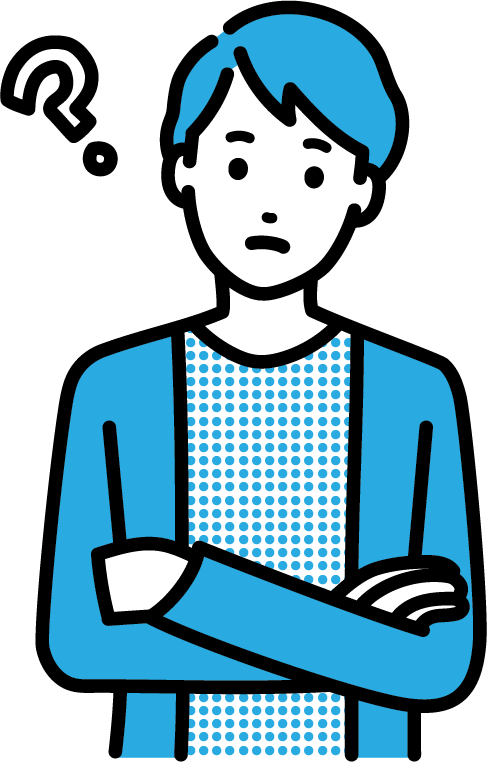
相談者様
埼玉県と神奈川県にあります。

行政書士
そちらの地域だと関東運輸局管轄の条件が適用されますので、詳しく解説します。
管轄について
冒頭の会話にあるとおり、ディーラーナンバーは地域によって取得条件が異なります。
地域については、次の11つにわかれており、埼玉や神奈川は関東運輸局管轄になります。
| 管轄 | 事務所の所在地 |
|---|---|
| 関東運輸局管轄 | 東京都・埼玉県・茨城県・栃木県・千葉県・神奈川県・群馬県・山梨県 |
| 北海道運輸局管轄 | 北海道 |
| 東北運輸局管轄 | 青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県 |
| 北陸信越運輸局管轄 | 新潟県、長野県、富山県、石川県 |
| 中部運輸局管轄 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県 |
| 近畿運輸局管轄 | 大阪府、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県 |
| 神戸運輸監理部管轄 | 兵庫県 |
| 中国運輸局管轄 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国運輸局管轄 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州運輸局管轄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
|
沖縄総合事務局運輸部管轄 |
沖縄県 |
ディーラーナンバーは、この11つの運輸局管轄ごとに定められています。
ちなみにここでいう事務所というのは、ディーラーナンバーを管理・保管する事務所の事であって、個人の自宅や法人の本店所在地以外の場所でも問題ありません。
関東運輸局管轄の取得条件
ディーラーナンバーは、使用する目的によって条件が異なります。
使用する目的については、次の4種類です。
| 用途 | 対象事業者 | 実例 |
|---|---|---|
| 製 作 | 自動車メーカー、架装事業者など | 自社工場からの回送など |
| 販 売 | ディーラー、中古車販売業者など | 仕入れ先からの回送など |
| 陸 送 | 陸送事業者 | 委託者が指示した回送など |
| 特定整備 | 自動車整備事業者 | 車検場までの回送など |
「製作」で許可取得する際の条件
「製作」による回送とは、自動車メーカーや架装業者が自動車を工場などから回送する場合に取得する許可で、条件は次のとおりです。
- 直近3ヶ月における月平均製作台数が10台以上であること
メーカーや自動車の架装を行う事業者が取得することを前提としています。
自社で製作・架装をおこなった車両が、1ヶ月平均して10台以上であれば条件クリアとなります。
平均の対象となる期間は、申請する月の直近3ヶ月です。
対象期間について、申請月を含めるのか含めないのか、どのような書類を提出するのか等は
申請先の陸運局によって多少異なるかと思います。
一般的に架装や製作の実績は「架装図面」や「架装契約書」を提出することによって証明します。
「販売」で許可取得する際の条件
「販売」による回送とは、自動車販売業者が販売のために自動車を整備工場や別の店舗へ移動させる場合に取得する許可で、条件は次のとおりです。
- 直近3ヶ月における月平均の販売実績が12両(大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分としてカウント)以上であること。
- 古物商の許可を取得している事(中古車を販売する場合のみ)
「販売」の条件も「製作」と似ていて、自社で販売した車両が1ヶ月平均して12台以上であれば条件クリアとなります。
なお大型のトラックやバス、外車はポイントが高いようで、1台販売すれば2台分のカウントをすることができます。
オークションで販売した場合についても、それを証明できる書類があれば恐らく実績にカウントできると思われますが、こちらも陸運局によって多少扱いが異なると思われます。
ちなみに販売の実績は「売買契約書の写しや注文書の写しなど」を提出することによって証明します。
オークションの場合は、オークションの運営者から発行される販売証明書等の書類を提出する必要があるかと思います。
また、中古車に限らず中古品を仕入れて販売する業態の場合は、古物商の許可が必要となりますので、持っていない場合は取得する必要があります。
「陸送」で許可取得する際の条件
「陸送」による回送とは、他人の依頼を受けて回送費をもらって自動車を運ぶ場合に取得する許可です。
陸送は、さらに3つの業態に分かれ、条件も次の通り異なります。
運送事業者の場合
- 製作又は販売を業とする者と自動車の回送委託契約を締結していること。
- 回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
- 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
- 回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。
こちらは一般貨物運送事業者がディーラーナンバーを取得する際に課せられる条件です。
①はそのままです。
少なくとも1社以上の自動車メーカーや車屋さんと、自動車の陸送に関する契約を結ぶ必要があるという事です。
②はおそらくディーラーナンバーの貸し借りを禁止する趣旨の規定かと思われます。
③もそのままで、①の契約は1年以上の期間で契約しなさいという趣旨です。
④については、少なくも1人運転手を雇用し、さらに1台以上積載車(キャリアカー)を保有している必要があるという事です。
運転手については分かるのですが、積載車を持っている事とディーラーナンバーを使用することの因果関係が無いように感じるため条件の趣旨が不明です。
運転手については、個人でディーラーナンバーを取得する場合はその事業主、法人で取得する場合は代表者で問題ないとする陸運局が多いと思います。
申請の際は「回送委託契約書(写)」「運転手の免許証(写)および雇用契約書(写)」「積載車の車検証(写)」などを提出することによって証明します。
港湾荷役に伴う陸送を業とする場合
- 製作又は販売を業とする者と回送委託契約を締結していること。
- 回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
- 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
- 回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること
こちらはおそらく自動車の輸出する際に、貨物船に載せるため埠頭にて車両を自走させる場合のみを想定しています。
該当する事業者様は限られるでしょうが、港湾荷役のみに使用するのであれば条件が緩和されるという事のようです。
その他の場合
- 製作又は販売を業とする者と回送委託契約を締結していること。
- 回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
- 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
- 回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。
「陸送」のほとんどの場合、こちらの「その他」に該当すると思われます。
基本的な条件は上2つと同じですが、確保しなければならない運転手が10人と多くなっています。
ここで気になるのが、個人で「陸送」でのディーラーナンバー取得ができるのかという事です。
企業であれば従業員が10人いらっしゃる場合もあると思いますが、個人事業主として働いている方で授業員を10人以上雇用されている方は稀だと思います。
かといって個人で運送業の許可を取得することもそれはそれで難しいため、個人で「陸送」でのディーラーナンバー取得が、現実的に難しいという事になります。
「特定整備」で許可取得する際の条件
「特定整備」による回送とは、自動車の認定整備工場が車検のために移動させる場合に取得する許可で、条件は次のとおりです。
- 初めて申請する場合・・・直近1年間において、自ら整備した車両の車検に係る第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
- 2回目以降の申請の場合・・・申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること。
「特定整備」の場合は、はじめて新規で許可を取得する場合と、許可を更新する場合とで条件が異なります。
ここで記載されている「第35条の臨時運行許可」というのは、市役所等で発行される仮ナンバーの事です。
仮ナンバーは車検切れの車両が公道を走れるという点ではディーラーナンバーと同じですが、借りられる期間や手数料に違いがあります。
つまり自分で整備した車を仮ナンバーを使って回送した実績が1年で7台あれば「特定整備」の条件を満たすという事です。
なお、許可の更新の際は既にディーラーナンバーを使っているので、わざわざ仮ナンバーを使う事はないため、ディーラーナンバーによる回送実績7台となっています。

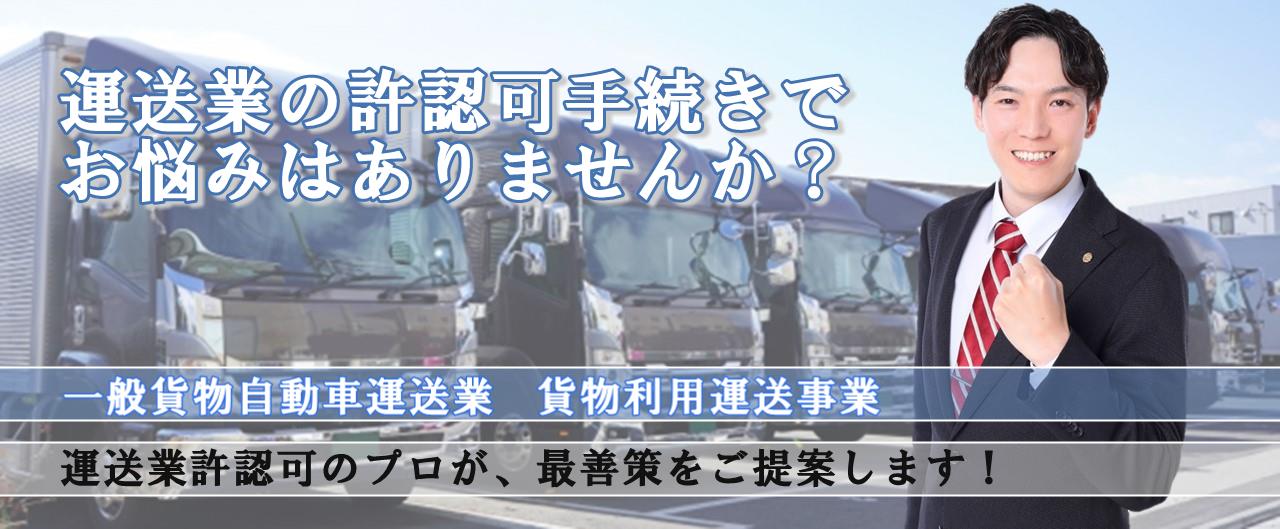
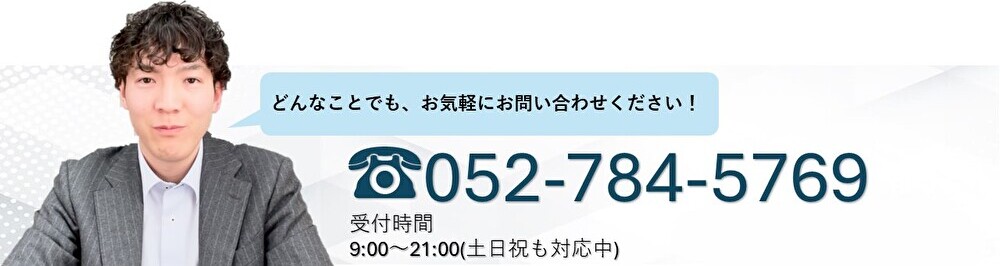



.jpg)


